宿題にも色々ありますが、確かなのは、ただやらせれば良いというものでは無いということでしょうか。宿題にもいくつか種類があって…
1)一問一答や計算ドリルなどの演習系課題
2)問題集やワークブックで、その日の授業で学習した部分を課題とする
3)問題集やワークブックで、これまで学習してきた部分を課題とする
4)授業でやり残したこと(まとめとか)
5)好きなことをやっておいでという丸投げ
6)その他いろいろ
1~5で共通していることは、「分からないものは分からない」ということです。間違いをそのまま繰り返しドリルしたり、よく意味を分からないでまとめたり写したりする作業をしてしまうと、間違いが定着します。わからないことを必死に調べていたら、それだけ時間を消費(浪費)します。しかも、わからないままで終わるでしょう。分からないことだらけだと、意欲と興味を失います。
次に、宿題の目的です。
1)授業で学習したことを定着させるため
2)授業でやり残したことをカバーするため
3)家庭学習の習慣を定着させるため
4)理解していないところを確認するため、させるため
1番が目的であるなら、授業で確実にできるようにしてから出す必要がありそうです。授業で習ったことをもっとたくさん練習したい!とか、もっとしっかり身に付けたいと感じさせたいところです。2番が目的であるなら、授業の再構築が必要かもしれません。3番が目的であるなら、時期と程度を考える必要がありそうです。4番が目的であるなら、一人一人異なってはいるでしょうが、理解できていないところをしっかり補習する必要がありそうです。
さくら塾で宿題を出すとしたら、
理解していないところを確認するために、一問一答や計算ドリルなどの問題を課題として、次の授業で理解できていないところをしっかり理解させます。そして、理解していないところを確認するために、一問一答や計算ドリルなどの問題を課題として出して…. 社会や理科、英語など、場合によっては、単語や用語の一覧表や、理解を助けるワークシートを覚えておいでと渡します。
目標の設定ってとても大切だと思います。課題は何でも良いと思います。
稀に、20人や30人、40人の児童生徒のみんな(ほぼ100%)を伸ばすことができる先生がいらっしゃいますが、本当に凄いと思います。そのような先生は宿題の扱い方も明確な目的や意図があります。自分は一斉授業ではそういう教員になれないかもしれません(なれるかもしれません)が、せめて個別指導ではしっかり伸ばせる教員でありたいと思います。
宿題について文章をまとめていたので書いてみました。考え方は人それぞれありますので、断定した書き方は避けています。また、何かを意図したり、誰かをイメージして書いてはいません。

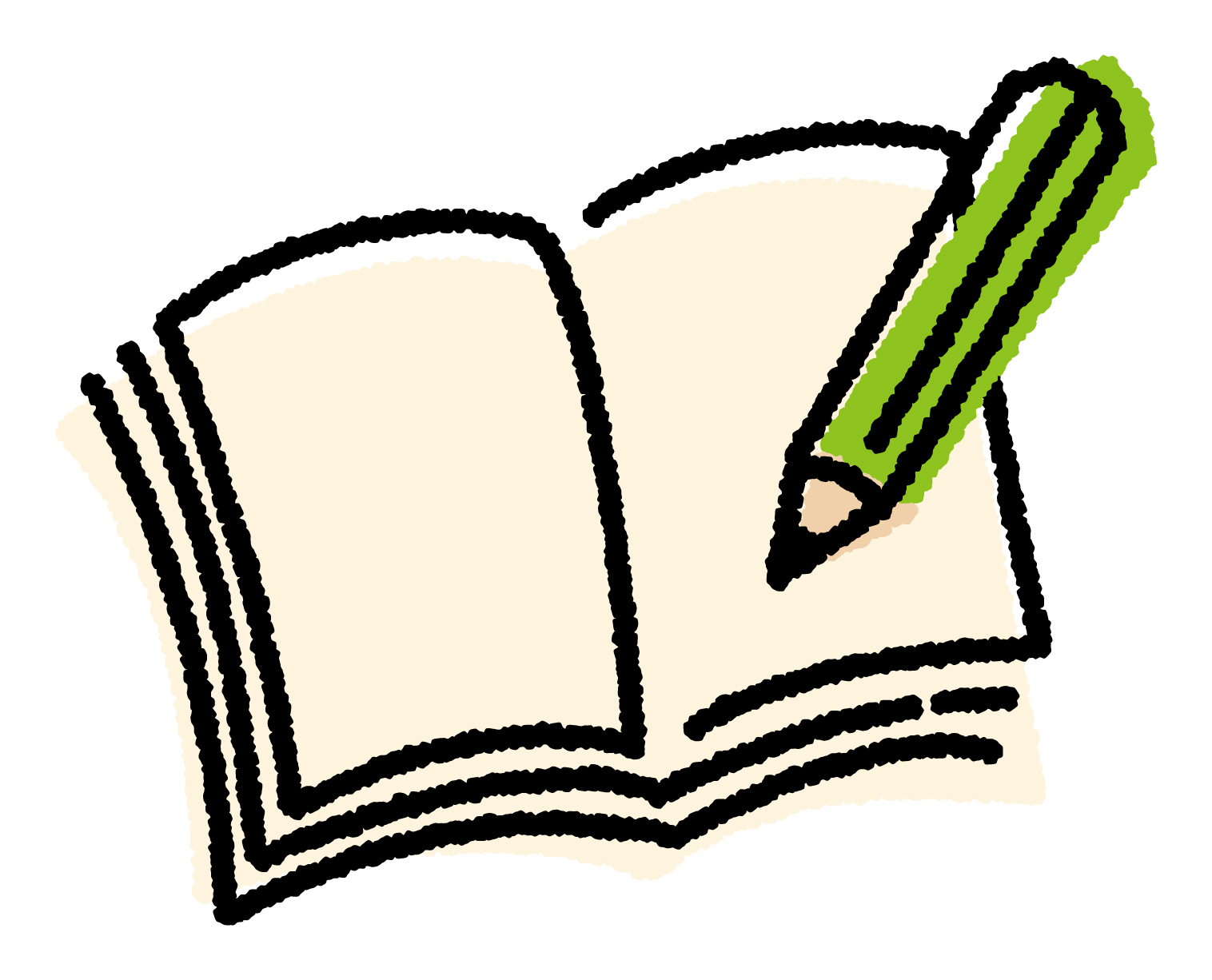
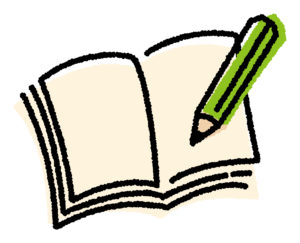


コメント